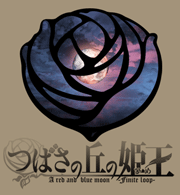| 『つばさの丘の姫王』 発売一周年記念ショートストーリー 「地底温泉 ふしぎの宿」 by 六花梨花 |
|
地の底――そこは、闇の精霊、ドワーフ族、ゴブリン族、その他、魔物の類が住まう場所。日の当たらぬ場所で暮らす者達の、水晶やアメジストが煌めく暗闇の世界……のはずなのだが。 「ほう……」 くるりと周りを見渡し、ヴィヴィアンは感嘆の声を漏らした。 そこは本当に地の底かと疑いたくなるような景色が広がっていた。 本来なら漆黒の闇である天井は、薄いグレイの雪雲に覆われた空が広がり、ご丁寧に光量も地上の昼の曇天になるよう調節されていた。 そこからゆっくり静かに、しんしんと白い雪が舞い散り、木々や石灯籠、立派な木製の門の上に、ふんわりと体積し続けている。 「凝っているな。絵や写真で見た、日の本の風景と同じだ。 この空間、すべて魔法で造られているのか」 「建築物は、ドワーフ達が手がけたようだな」 石灯籠をつんつんとつついているヴィヴィアンに、ダウスがそっけなく言葉を投げる。 「壊すなよ」 「ふん、そっちこそ」 二人は並んで、宿の門をくぐった。 最後のフェニキアクスを超えて自由になったというのに、ダウスは自らの意思で執事姿のまま、ヴィヴィアンの元にいることを選んだ。 そのダウスが、ヴィヴィアンに突きつけたものは―― 「出来たてほやほやの地底温泉に、ご招待。 このチケットで二名様までご来場いただけます。 温泉の本家、日の本風に徹した新感覚のアミューズメントホテル『ふしぎの宿』へ是非お越しください」 「という訳だ」 「何が、という訳なんだ? ちゃんと素直に言うといい」 「そうか。では、別の者と行くとする」 「お前と一緒に行ってくれるような相手がいるのか?」 「だったら、素直にお前がついてこい、小娘」 「仕方がないな。素直になれない頑固爺の為に、私が折れてやるとするか。 で、いつからだ?」 「今すぐだ」 ダウスが三回、靴の踵で床をノックすると、ぱこんと真円の穴が開いた。 躊躇なく、老執事は自分が開けた黒穴へと飛び込む。 「相変わらず、せっかちな年寄りだ」 微笑しながら、ヴィヴィアンも後に続いた。 「……この、記帳とはなんだ」 「代表者様と、お連れ様のお名前とご住所を書いていただくものでして」 問いに答えた着物と羽織姿のドワーフを、ダウスはぎろりと睨みつけ、くわっと口を開いた。 「貴様もドワーフなら、儂らがどこの誰か、わかっているだろう。わざわざこんなものを書かせるな!」 「ひ、ひい、旅情を味わっていただく為のシステムなんですよぅ!」 「サインくらい、ささっと書いてやればいいだろう。それとも何か? いつから文字が書けなくなったのだ?」 「ええい、うるさい、黙れ」 「まったく、しかたのない老人だ。では、私が書いてやるとしよう。夫の欄が私で、妻の欄がお前でかまわんな」 「おかしいだろう、それは、とってもおかしいだろうが!」 「なんでもいいから、早くしてくださぁい! だから、そんなに睨まないでくださいよぉ、夜闇の王!」 通された部屋は大きな和室で、こたつや座椅子などが設えてあった。 「こたつは無限図書館で体験済みだが、畳は初めてだ」 目をきらきらさせたヴィヴィアンは、ゆっくりと畳を踏みしめた。 「ふむ。不思議な感触だ」 「風呂が先でいいな。メシは後にするぞ。大浴場と内風呂があるようだが、どっちだ?」 「どう違うのだ?」 部屋に備え付られた案内冊子のページをぺらりと捲ってからダウスが言う。 「大浴場は、男女別で、でかい風呂がいくつか。内風呂は混浴で露天風呂だそうだ」 「髪を洗ってくれるのなら、内風呂にしてやろう。たまには爺孝行だ」 「別に頼んでおらん」 「そんなことを言うと、大浴場へ行ってしまうぞ?」 廊下に出る障子の引き手へと伸ばしたヴィヴィアンの手を、ダウスは掴み、ぐいっと引き寄せる。夜光の王が何か言う前に、素早くドレスのボタンに手をかけた。 「素直じゃないな」 「うるさい。お前が一人で脱げんのが悪い」 「脱げるが、人にして貰う方が好きなだけだ」 「横着者め」 「その横着者の躰も洗わせてやろう」 「無論、そのつもりだ。絶対に一人では洗わせてやらん」 むすっとした顔のまま、甲斐甲斐しいことを言うダウスの様子に微笑しつつ、ヴィヴィアンは紋章を模った白いネクタイ留めに手をかけた。 外に面した障子を開くと、そこには日の本風の小さな庭園が広がっていた。 玄関にあったものより、かなり小振りの石灯籠。自然石に簡単に穴を開けたつくばいに、鹿威し。真っ赤な花がたくさん咲いている椿の木々。すべてに雪化粧が施されているその向こうから、うっすらと湯気が流れてくる。 「これが、露天風呂か」 一抱えほどある岩をいくつも重ね、ぐるりと囲いがされている中で、白く湯気をたてている温泉を見て、ヴィヴィアンがはしゃぐ。 夜光の王とは対照的に、静かに風景を眺めていたダウスは、湯船の影に目を落とした。 「酒が用意されているな。これを持って、入ってもいいということか」 「日の本の酒だ。これはいい。さっさと風呂に入って楽しむとしよう」 「待て、まずは躰を洗ってからだろう」 「律儀だな、夜闇の王は」 「お前が大雑把過ぎるのだ。ここは森の中の泉とは違うのだぞ。マナーを守れ、マナーを」 躰を洗って貰ってから、ざぼんと湯に浸かると、ヴィヴィアンは蕩けそうな吐息を漏らした。 「はあ……。躰が芯から温まる」 寛いでいるヴィヴィアンの隣に、ダウスもゆっくりと身を沈めてから、酒の入った徳利や猪口の乗った盆を、そっと引き寄せた。 「なるほど。こうして楽しむものだったのか。早くくれ。早く」 「どうしてそう、せっかちなんだ。ほれ」 猪口に注いで貰った酒を、ヴィヴィアンは喉奥へと落とす。 「うむ、風呂の中で飲むのも格別だ」 「少し辛口だな」 猪口の中の酒に映る空を見て、ヴィヴィアンは僅かに目を細くした。 「……不思議だ」 「何が」 「曇天は嫌いだった。雷が鳴ることがあるから。鳴れば……」 「戦いが始まることが多い」 「ああ、そうだ。だから嫌いだった。だが、今は違う。こうして穏やかに空を見ることが出来る。無理に戦わされる元凶だった者と並んで、酒を飲んでいるのが……本当に不思議だ」 「……ふん」 「こんなに穏やかな日が、私に訪れるとは思っていなかった」 「儂の手を取っておれば、同じように穏やかな日々を迎えていたかもしれんというのに」 「私は私のしてきたことを否定する気はない。だから、これで良かったのだ」 ふん、と再び鼻を鳴らしつつ、ダウスは一口、酒を飲むと、大きな掌でヴィヴィアンの頭をくしゃりと撫でた。 揃えの浴衣が置いてあるが、どうやって着てよいかわからないでいるヴィヴィアンを見かね、ダウスが着付けてやると、夜光の王はほくほく顔でくるりと一回りした。 「これが浴衣か。エキゾチックでいいな!」 「こら、髪が濡れたままだとメシを食う時に邪魔だろう。乾かして、くくっておけ」 ふむ、と、考えてから、ヴィヴィアンは鏡台の前に腰掛け、ダウスに櫛を手渡した。 「お前がやれ」 「まったく……どんな髪型になっても知らんぞ」 優しく乾かしてから、ダウスは器用に金色の髪を結っていく。 「おや、これは……」 「こんな髪型をしていた頃があっただろう」 鏡に映るツインテールにされた姿を、ヴィヴィアンはまじまじと見つめる。 「子供の頃は、よくこんな風にして貰っていたが、この年の容姿になってからするとは思ってもいなかった」 「いやなら、自分で直せ」 「断る。気に入ったから、このままでいる」 鏡台の前から立ち上がると、ヴィヴィアンは鼻歌を歌いながら襖を左右に開いた。 「まだ夕食は用意されてないな」 「もう少しかかるのだろう」 すっと無駄のない身のこなしでこたつに入ると、ダウスは急須を手にした。 「私にもくれ」 「わかっておる。座れ」 角を挟んだダウスの隣に、ヴィヴィアンもするりと入った。 「ふう、暖かい。こたつは魔物だな。入ってしまうと出るのが難しい……」 とろりと夢見心地でいるヴィヴィアンの目が、茶菓子の前で止まった。 「この饅頭や蜜柑は食べていいのか?」 「かまわんだろう。……ん。茶柱が立った」 「なんだ、それは?」 ダウスは湯飲みの中を、ヴィヴィアンに見せた。 「小枝の先のようなものが縦に浮いているな……。これが、茶柱か?」 「一般的にはそう言われておるがな。湯気が柱のようになる現象という説もある」 「ふーん。不思議だ。こんなの見たことがないぞ。どうして、お前は知っている?」 「伊達に長いこと、無限図書館に封じ込められてはおらん」 「なるほど。そこで得た知識か」 自分の饅頭をぺろりと平らげたヴィヴィアンは、まだ机の上に残っているダウスの饅頭に目をやった。 「饅頭、美味しいぞ。食わんのか? 食わんのなら、食ってやろう」 「欲しいなら素直にそう言え。だが、そんなに食ったら夕食が……お前は食えるな」 「ああ。私を誰だと思っている」 ヴィヴィアンは堂々とダウスの饅頭を奪い、口に運んだ。 無邪気に饅頭を食べている夜光の王の横で、夜闇の王は包み紙を結び守文型に括っている。 「うん、美味いな。皆のお土産に買っていってやろう。 ついでに、この茶器セットも売っていたら買って帰る。茶はお前が淹れろ」 「自分でしろ」 「お前がしろ」 こたつの中で、膝同士を小突き合わせながら言い争いつつも、二人の雰囲気はとても柔らかい。 「夕食を食べたら、付近を散策でもするか? それとも、フロント前の土産屋を覗くか?」 「そんなに急ぐ必要もないだろう」 「そうだな。たまには、こんなところでのんびりするのも良い」 こたつの中に入ったまま、ヴィヴィアンは、んっと手を伸ばし、障子を少しだけ開ける。 5センチほど開いた向こうでは、相変わらず雪が静かにしんしんと降り、すべての音を吸い取り、耳が痛くなるほどの静寂をもたらしている。 「静かだな」 「ああ、そうだな」 二人は膝をくっつけあったまま、ゆったりとした時間に身を委ねた。 |
| 【おしまい】 |